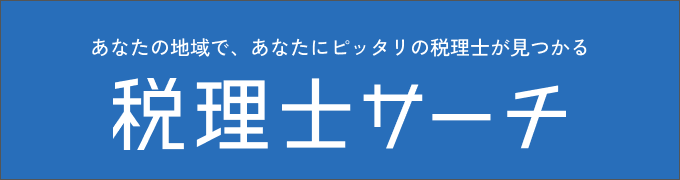近年、「タワマン節税」という言葉を耳にする機会が増えました。
市場価格と相続税評価額の差を利用する相続対策です。
しかし、令和7年11月13日に国税庁が公表した説明資料「財産評価を巡る諸問題」を見ると、議論の焦点は区分マンションにとどまっていないことが分かります。
現在、国税庁が注視しているのは、
一棟所有の賃貸マンションなど「貸付用不動産」を活用した相続税対策
です。
1.なぜ貸付用不動産で評価差が生じるのか
資料7頁では、貸付用不動産の市場価格と通達評価額の関係が整理されています。
市場価格
- 収益性が高い
- 入居率が高い
- 安定した賃料収入
→ 収益物件として人気が高まり価格上昇
相続税評価(通達評価)
- 借家人の権利を考慮
- 利用・処分の制約を評価に反映
→ 入居割合が高いほど評価は下がる
結果として、
人気物件ほど市場価格は高く、税務評価は低くなる
という逆転現象が生じます。
この評価差(かい離)が、さまざまな相続対策に利用されています。
2.最高裁判決に至った事例
資料4頁では、次の事例が紹介されています。
- 13.8億円で賃貸物件取得
- 通達評価額3.3億円
- 借入金10億円を債務控除
- 相続税0円申告
取得価額と通達評価額の差は10.5億円。
この事案は令和4年4月19日の最高裁判決につながりました。
最高裁は、
実質的な租税負担の公平に反する場合には、通達評価額を上回る評価も許容される
との判断を示しています。
3.一棟賃貸マンションの「駆け込み取得」
資料5頁では、
- 21億円取得
- 通達評価4.2億円
- かい離16.8億円
- 税負担7.9億円軽減
という事例も紹介されています。
区分マンションの評価見直し後も、一棟所有物件は依然として個別判断の対象となっています。
4.贈与スキームへの拡張
資料6頁以降では、不動産小口化商品を利用した贈与事例も示されています。
- 3,000万円で取得
- 通達評価480万円
- 贈与税大幅減少
- その後ほぼ同額で売却
評価額が取得価額の約1/6となるケースも確認されています。
5.通達6項と予測可能性
資料2頁・3頁では、財産評価基本通達6項の適用と、納税者の予測可能性の問題が指摘されています。
通達6項は、
「通達評価が著しく不適当な場合」に個別評価を可能とする規定
ですが、その適用場面が必ずしも明確とは言えないため、専門家団体からも制度整備を求める意見が出ています。
6.相続税対策のもう一つの側面
資料8頁では、
- 高額借入
- 入居率悪化
- 固定資産税負担
- 相続人の資金繰り困難
といった実務上の問題も紹介されています。
相続税の圧縮だけに着目した場合、
別のリスクが顕在化する可能性があることも示唆されています。
まとめ
今回の国税庁資料は、
✔ 貸付用不動産の評価差
✔ 一棟物件スキーム
✔ 不動産小口化商品の贈与
✔ 通達6項の運用状況
など、現在の財産評価を巡る論点を網羅的に整理したものです。
相続税の評価は、「価格」だけでなく「制度」と「運用」によって決まります。
制度の枠組みと近年の動向を理解しておくことは、資産管理において重要な視点の一つといえるでしょう。
今後も税制や通達の動向を注視していきたいところです。